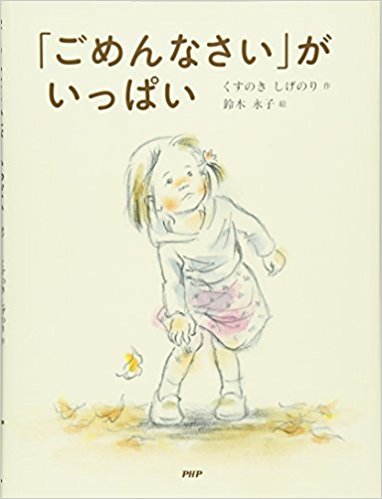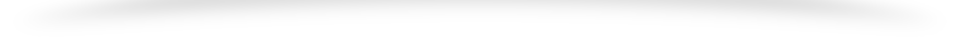あらすじ
「わたし」には、妹の「ふうちゃん」がいる。
お姉ちゃんだから、絵本を読んであげたり、数の数え方を教えてあげたり、面倒をよく見ていた。
しかし、ある夜、お父さんとお母さんが、心配そうに話をしていた。
「わたし」がふうちゃんの年頃にできていたことが、ふうちゃんにはできていないというのだ。
心配した両親は、ふうちゃんを病院に連れて行く。
すると、意外なことが分かったのだ──
小さい子にとって、自分のことを伝えることは難しい
主人公の「わたし」には、妹の「ふうちゃん」がいる。
面倒見のいい「わたし」はふうちゃんの面倒をよく見ていた。
しかし、ふうちゃんは、教えているのにも関わらず、数を数え間違えたり、走るときによく転んだりする。
そのたびにお父さんやお母さんや「わたし」に注意されて、ふうちゃんは「ごめんなさい」という。
どうもおかしいと心配になった両親はふうちゃんを病院につれていくと……彼女は強度の遠視だったのだ。
ふうちゃんはちゃんとやりたくても、ものが良く見えないので、たびたび数え間違えたり、転んだりを繰り返していたのだ。
ふうちゃんがどんな思いで「ごめんなさい」を言っていたのか、考えると胸が締め付けられる。
「わたし」も両親も、みんなでふうちゃんに謝る。悪気はなかったとしても、どんなにふうちゃんを傷つけていたか──それを思えばこその、自然な「ごめんなさい」だ。
きっと、謝られたふうちゃんのほうは、何のことかよく分からなかっただろう。だって、彼女にとって近くのものが良く見えないというのはいたって普通のことだったから。失敗するのは、自分が悪いのだと思っているから。
この物語は、彼女がメガネをかけて、それでハッピーエンドではない。
両親と「わたし」は、ふうちゃんが今まで繰り返してきた「ごめんなさい」を、自分のせいじゃないのだと教えてあげなくてはならないのだ。「ごめんなさい」を言った分、ふうちゃんの中では、出来ない自分が悪いと思い込んでいる。それは違うのだと、じっくり時間をかけて教えてあげなくてはならない。
それを思った上で、彼女の、
「おねえちゃん、『ごめんなさい』がいっぱいやなあ」
という言葉を聞くと、一層、ふうちゃんの健気さが伝わってくる。
ここから、ふうちゃん一家はやり直すのだ。ふうちゃんの、今までのような「ごめんなさい」が少しでも減るように。
みんなが泣き笑いしながら、「ごめんなさい」がいっぱいやなあ、というふうちゃん一家を見ていると、この家族はきっと大丈夫、という気持ちになってくる。
ふうちゃんは、きっと、自分に自信を取り戻していくだろう。
子どもは、分かりやすいようでいて、実際、全然分からないことだらけだ。
どんな饒舌な子も、自分のことをうまく伝えるすべを知らないときがある。
ちょっとした体調不良を、伝えることすら出来ない子もいるのだ。
子どものことを分かったつもりで接していると、思わぬ事情を抱えているのを知って愕然とすることがある。その抱えたものを瞬時にして察してやるのは、保護者でも難しい。
子どものほうは隠しているわけではないので、何かしらサインは出しているのだが、それを掬い取ってやることはとても難しい。
子どもと接するとき、私たちは、彼らをよく見て、些細なサインを見落とさないよう、心がけていきたい。
実際、これは言葉で言うのは簡単なことだ。
だが、つい、気づいたら、忙しさや、思い込みで彼らからのサインを見逃してしまうことが多いのが現実だ。
だから、再度、私たちは言い聞かせなくてはならない。
彼らをよく見て、向き合っていこう、と。
子どもよりもおとなが読みたい一冊
子ども向けに描かれてはいるが、子どもと接するおとなが読みたい一冊である。
気づき、というのがいかに大切で、難しいことか伝わってくる。
低学年向けではあるが、子どもと接するおとな向けといっても支障がない内容である。