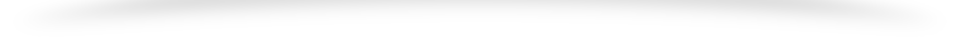感受性が強いのが子ども時代。
できるだけたくさんの本を読ませてあげたい……そう思いますよね。
本はどういった環境で与えていますか?
どういった状況で読ませていますか?
小学校低学年ぐらいまでは、何を読ませようかとか、これを読んでほしいなとか、いろいろ考えてしまいますよね。
子どもの教育に良くない本にはできるだけ、いや絶対に触れさせたくない!
そんな保護者のさまざまな思いの中で、幼年期から児童期の子どもは保護者から与えられた本と触れ合います。

残酷表現のあいまいな線引き
映画や本、ゲームには、年齢別のレーティングが設けられています。
えっちなものや残酷なものにはそれぞれ年齢制限や対象年齢を設けているわけです。
その他にも、この作品には残酷な表現を含みます、などといった注意書きが添えられているものも少なくありません。
でも、絵本はたまに「高学年向き」「三歳から」などと書かれているぐらいで、特にレーティングを定めていません。
しかし、絵本に残酷表現がないのかというと、そうでもありません。
むしろ、昔から伝わる昔話や、童話などには残酷な表現が山盛りです。
『かちかち山』だって『ヘンゼルとグレーテル』だって、人を食べたり殺したりします。『三匹のこぶた』ではオオカミを食べてしまう結末のものだってあります。大体の昔話や古典童話は、原型に近いほど、残酷な部分が増えていきます。
怖いですね。
だからこそ、完全に残酷表現を取り除いた昔話や童話が出版されたりもするのでしょう。
ところで、「残酷表現」とはどこからが「残酷表現」なのでしょうか。
血が出たら「残酷」? 人が殺されると「残酷」? 人が死ぬと「残酷」? じゃあ、戦争を取り扱った作品は?
明確な線引きがないですよね。「残酷表現」、実はこれは人によってラインがさまざまなのです。人によっては違うからこそ、「残酷表現」をめぐっての論争やトラブルが時に引き起こされるわけです。
そこで大事になってくるのは、保護者の方の「残酷表現」の線引きを明確にしておく必要があるのではないかと思います。保護者の方のラインがぶれていては、本の選定にもぶれが生じてしまいますから。

残酷表現を完全に規制したら
子どもの頃は管理できていたメディアとの接点も、長じるにつれ管理できなくなってきます。子どもは子どもの世界を持ちます。それはどうやっても防ぎようがありません。そこで、子どもたちは新たなメディアと出会います。
しかしそのとき、子ども自身の中に、「命は大切なもの」「人の痛みを知っている」というしっかりとした軸があったなら、残酷な内容のメディアと接したとき、「これは残酷な作品だな」としっかりと理解します。作品と現実の区別がしっかりとついているわけです。
その軸が育たなかった子は、長じてから残酷な内容のメディアと接したとき、どうなってしまうでしょう。
……考えるだけで恐ろしいですね。
残酷表現を完全に規制した中で育った子は、「残酷表現」の免疫が著しく低く、自分の中で残酷表現に対してどうするかということを判断する力も育っていません。ですが好奇心と感受性だけはひときわ強く、それらと「残酷表現」がどう化学反応を起こすかは誰にも分かりません。
世の中にはいろんなメディアが存在します。それはもう、思いも至らないような内容のものだってあるんです。それらとどう接するかというすべを、子どもの中で育んであげなくてはなりません。

どうやって「軸」を育むのか
どうやって「軸」を育むのか──その方法はいくつもあるでしょう。
その数ある手段の中で、「物語」という選択肢も存在していると私は思います。
「物語」は、読み手にいろいろな感情を呼び起こします。
喜びも怒りも、寂しさも悲しみも、そして大事な「共感」も、「相手の立場に立って考える力」も、「物語」は呼び起こしてくれます。
登場人物に感情移入して読めば、悲しい感情も、腹立たしい感情も、悔しい感情も登場人物と「共有」できます。
そうなって初めて、残酷な場面に遭遇したとき、呼び起こされるのは単なる好奇的な気持ちだけではなくなっているでしょう。
「物語」とともに、子どもの心の中に「軸」を育む。
その「物語」には、悲しみも怒りも苦しみも悔しさもなければ、子どもたちは負の感情について付き合っていくすべを学べません。負の感情にふたをして、明るく楽しくみんな幸せな「物語」だけでは、ひとそのものを知ることはできないのではないかと私は思います。なぜなら、ひとというものは、さまざまな感情を内包した生き物なのですから。明るいだけの片面を見て、ひととはこういうものだと教えることはできないのではないでしょうか。
かといって、無節操にすべての「物語」を許すべきだと私は言いません。
子どもの年齢に適さない刺激的な「物語」は思いもよらない毒になるでしょうし、年齢に対し幼すぎる「物語」は現実味のないものに受け取られてしまうことだってあるでしょう。
ある程度の年齢までは、おとなが本のナビゲーターとなり本の旅の同伴者となって、ともに歩んでいく──それがおとなにできる「力添え」というものではないでしょうか。